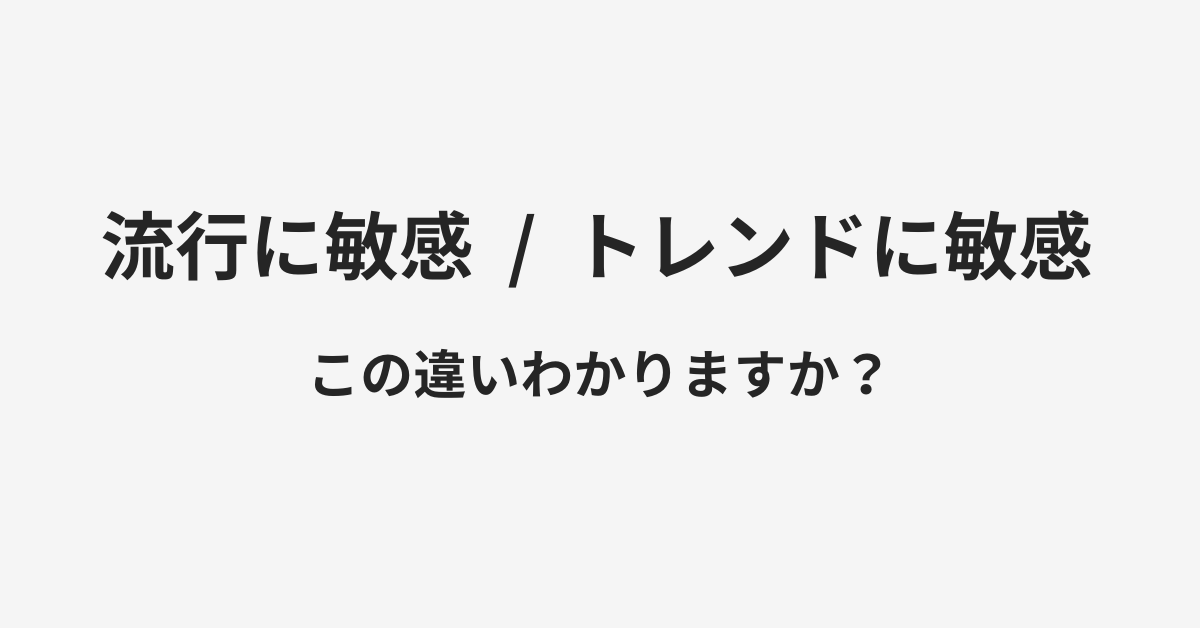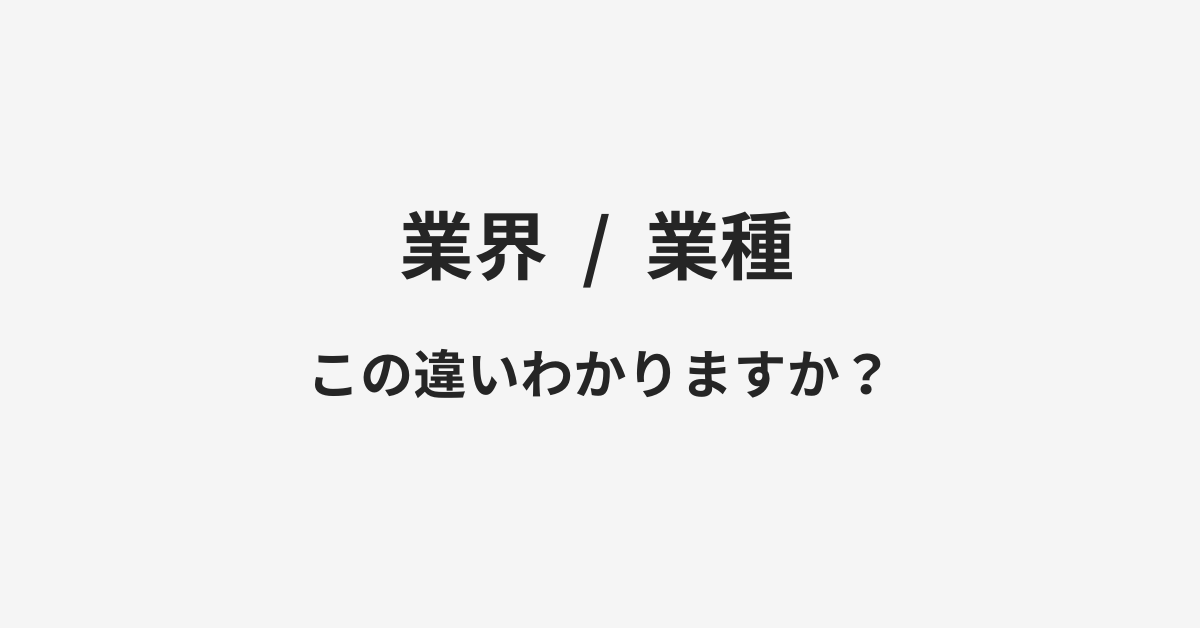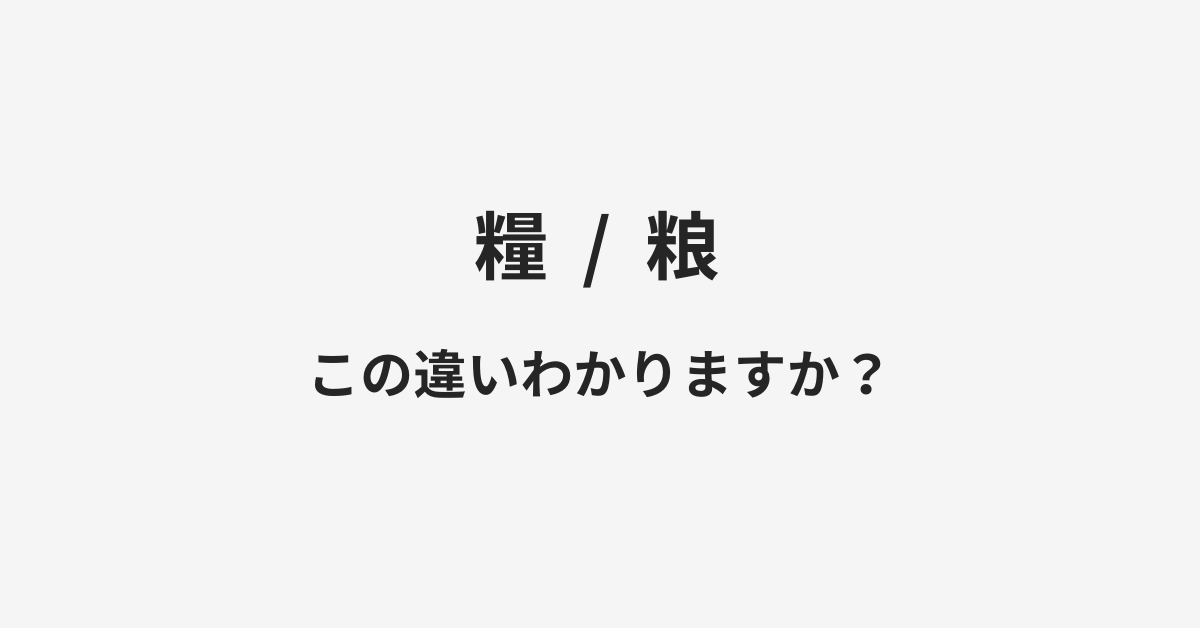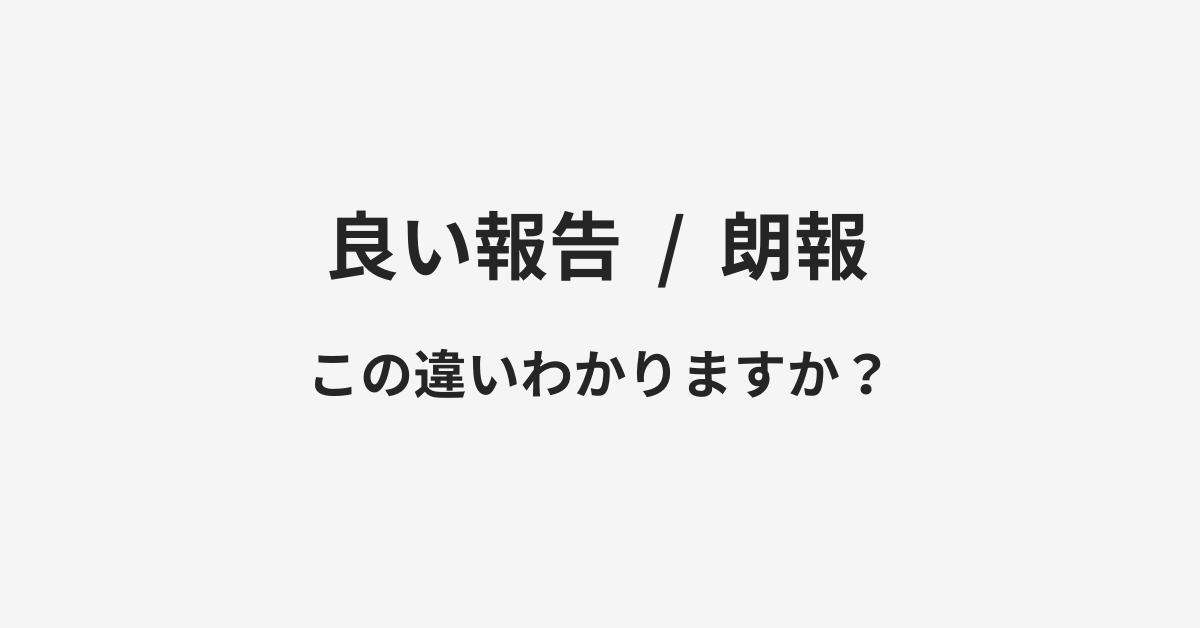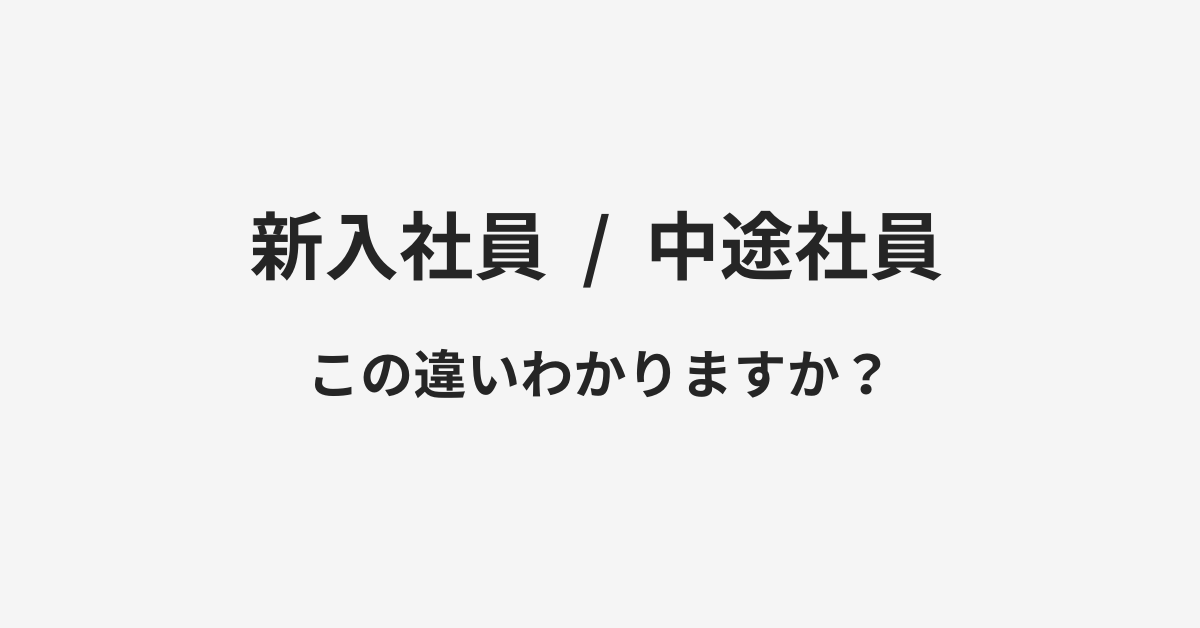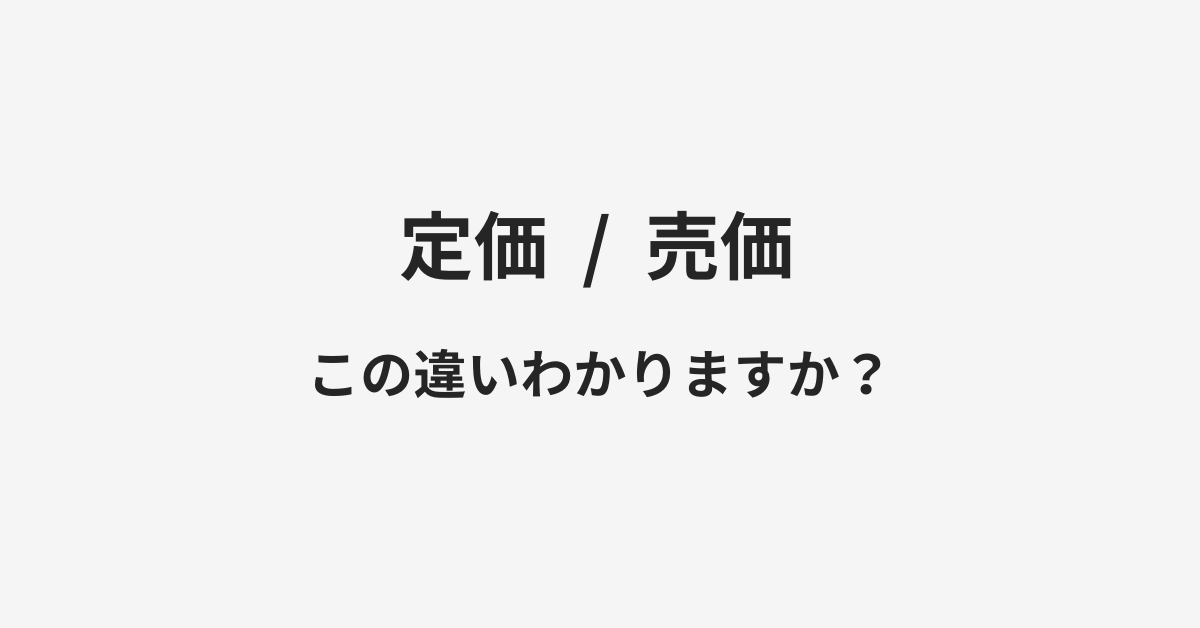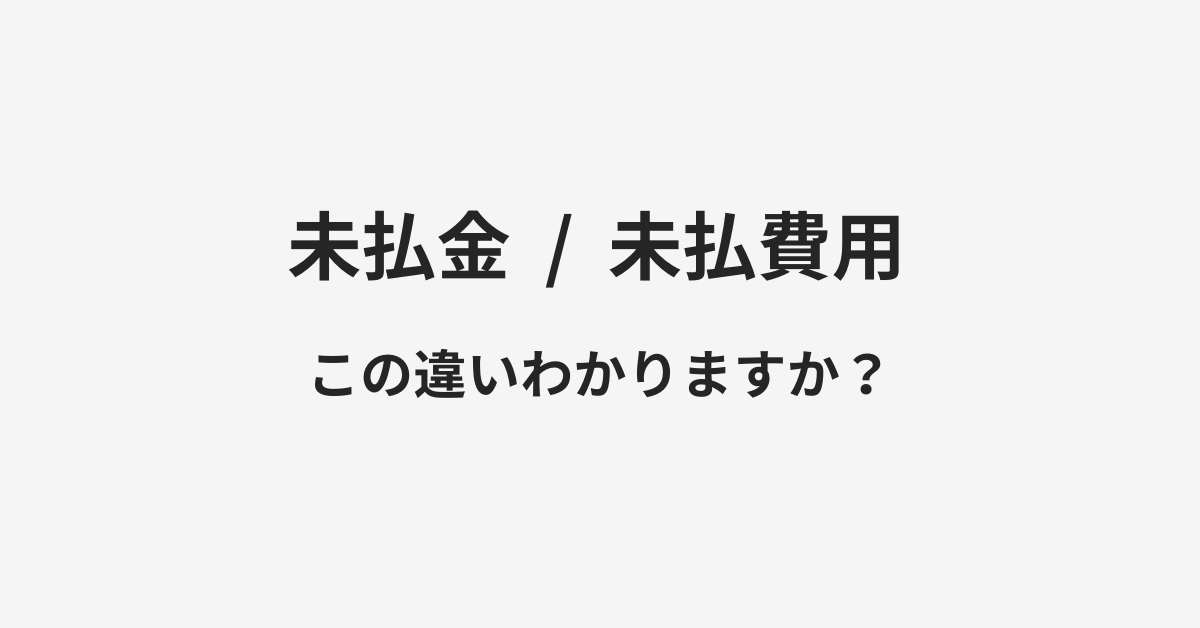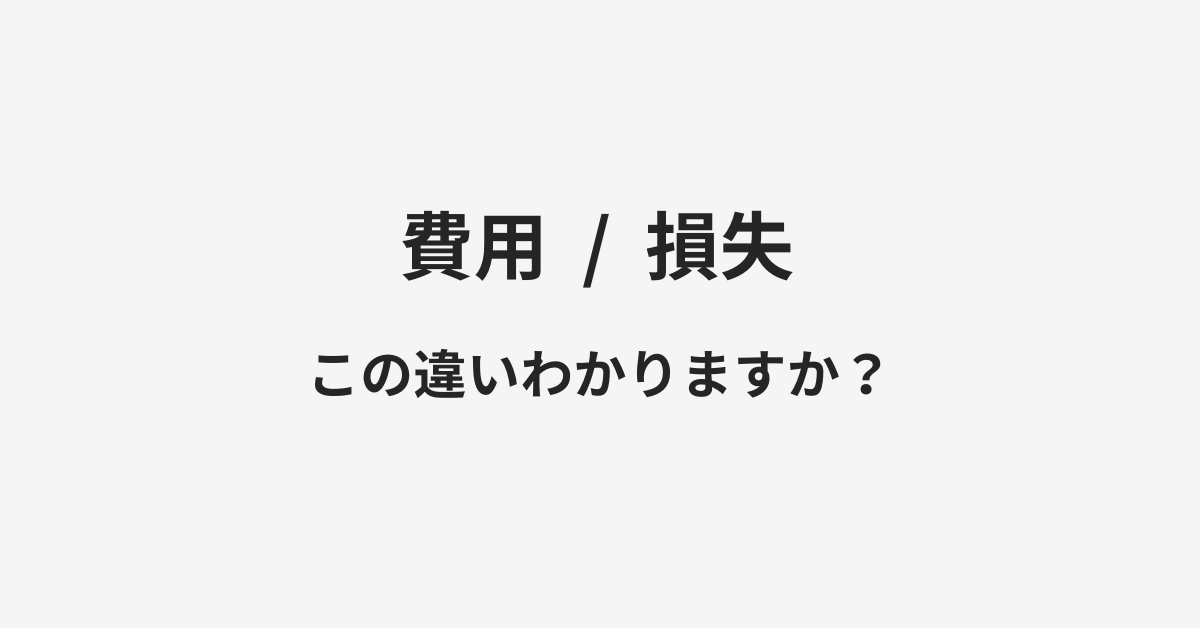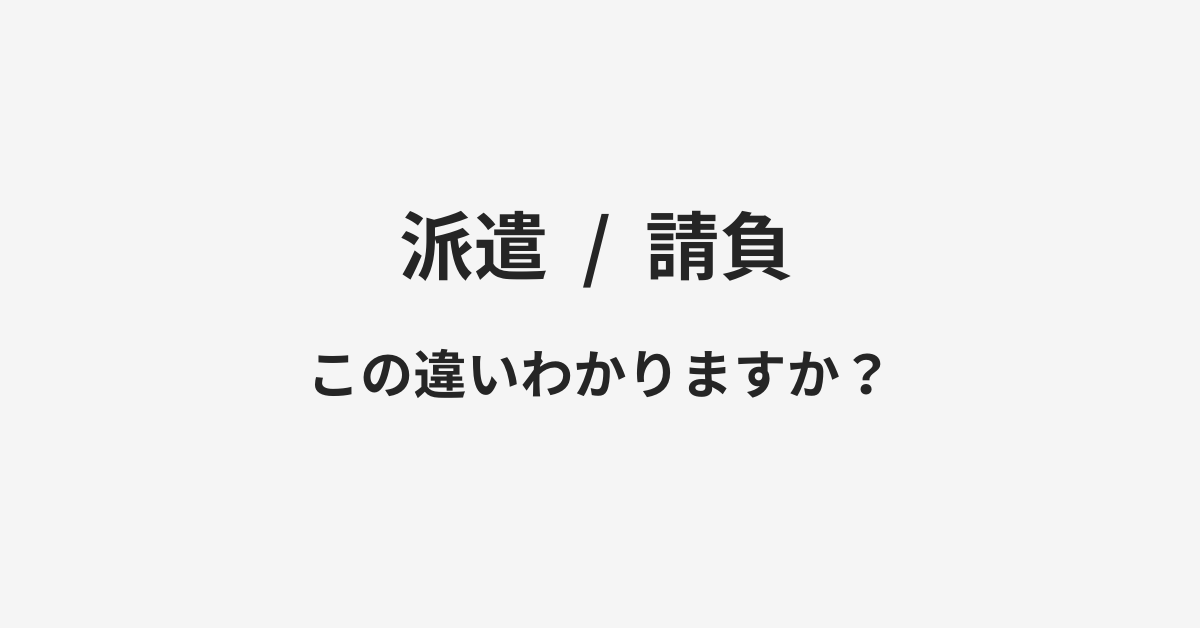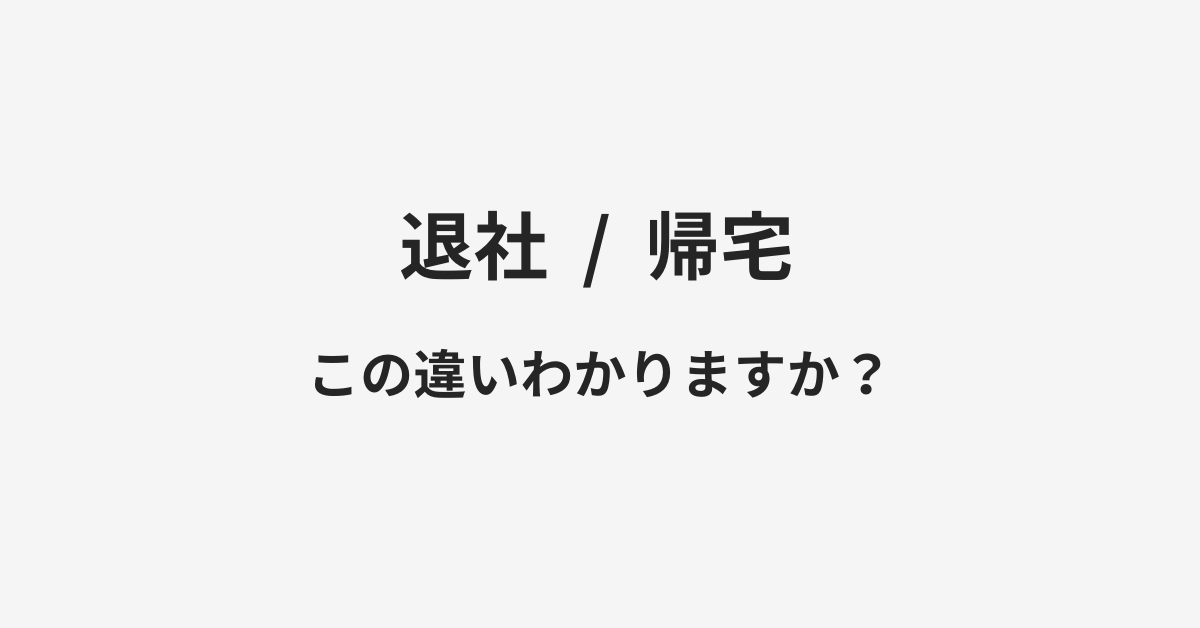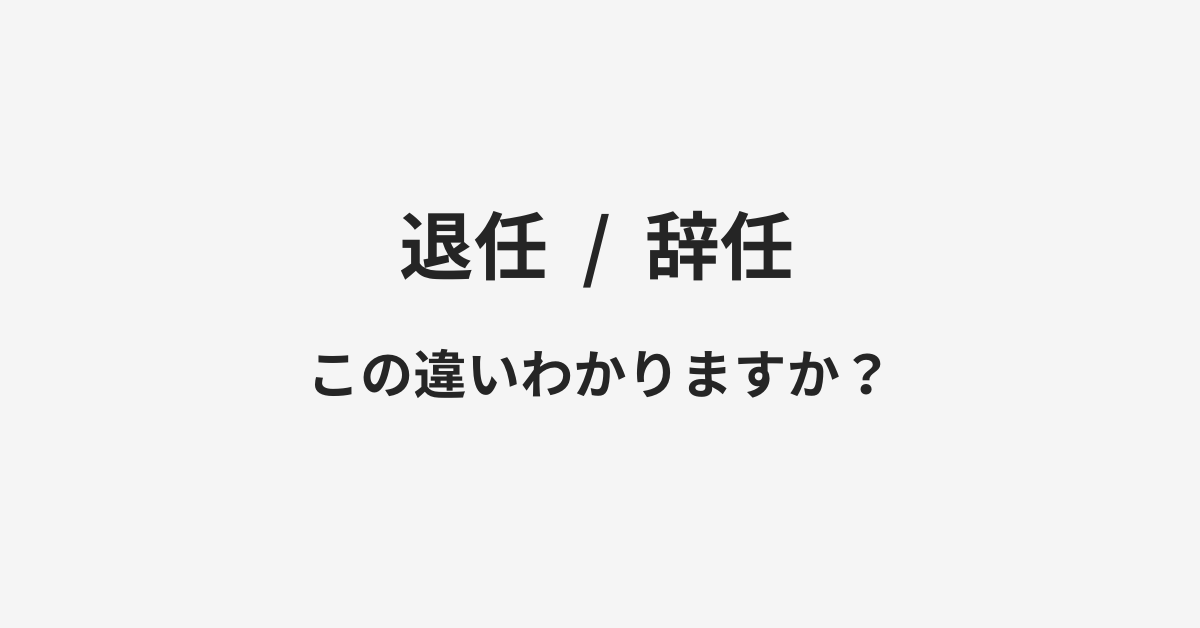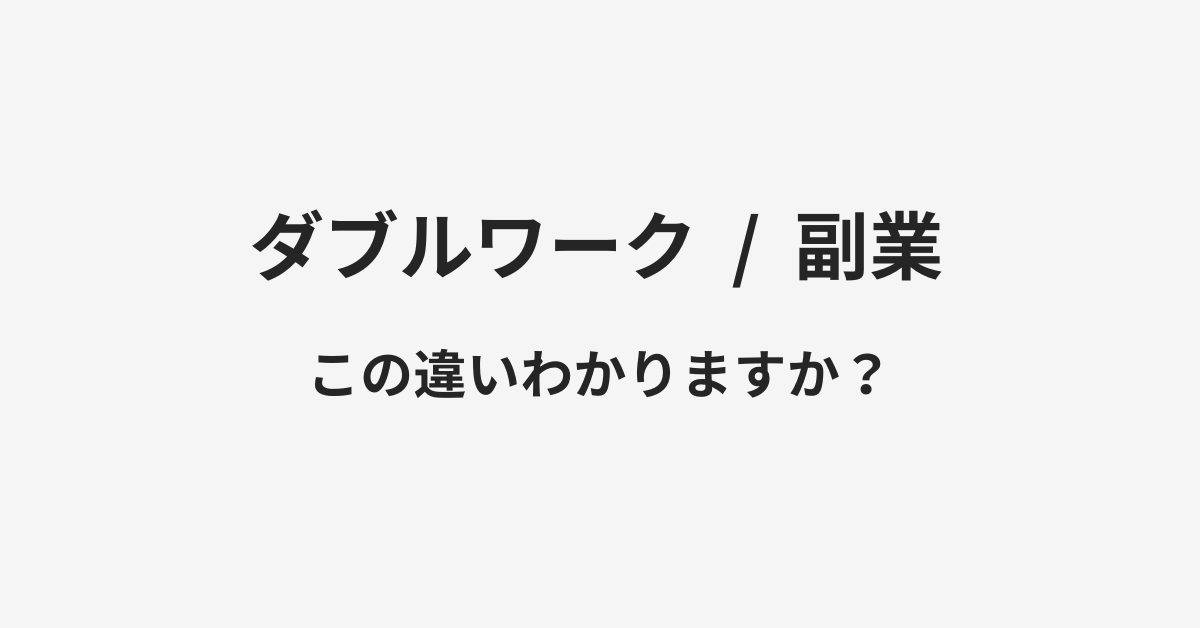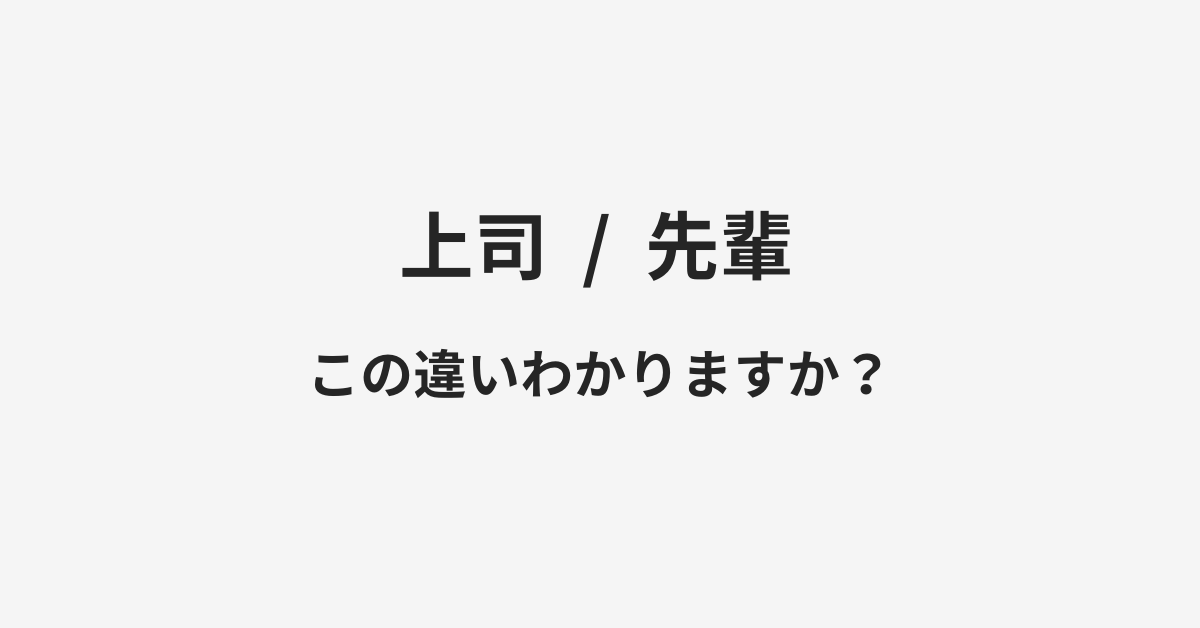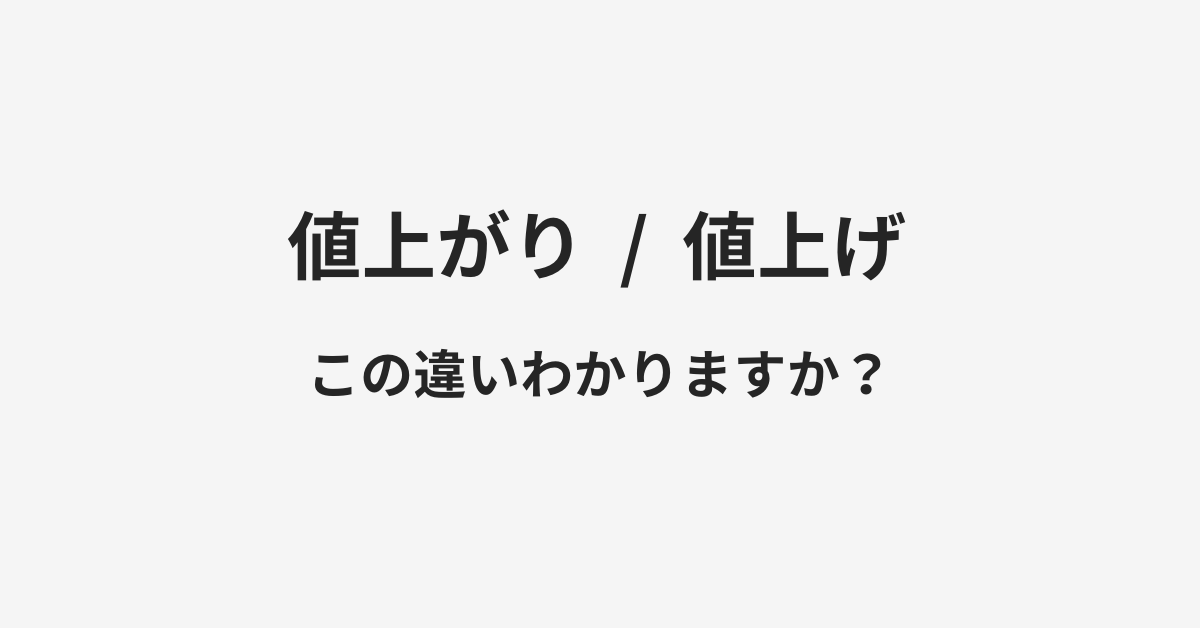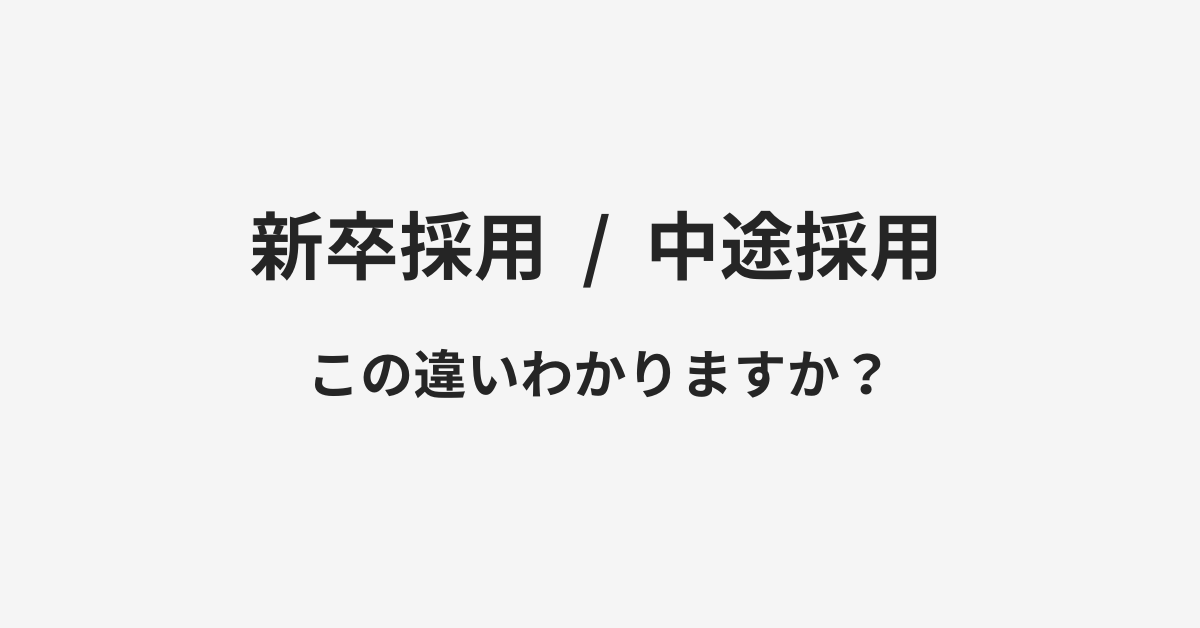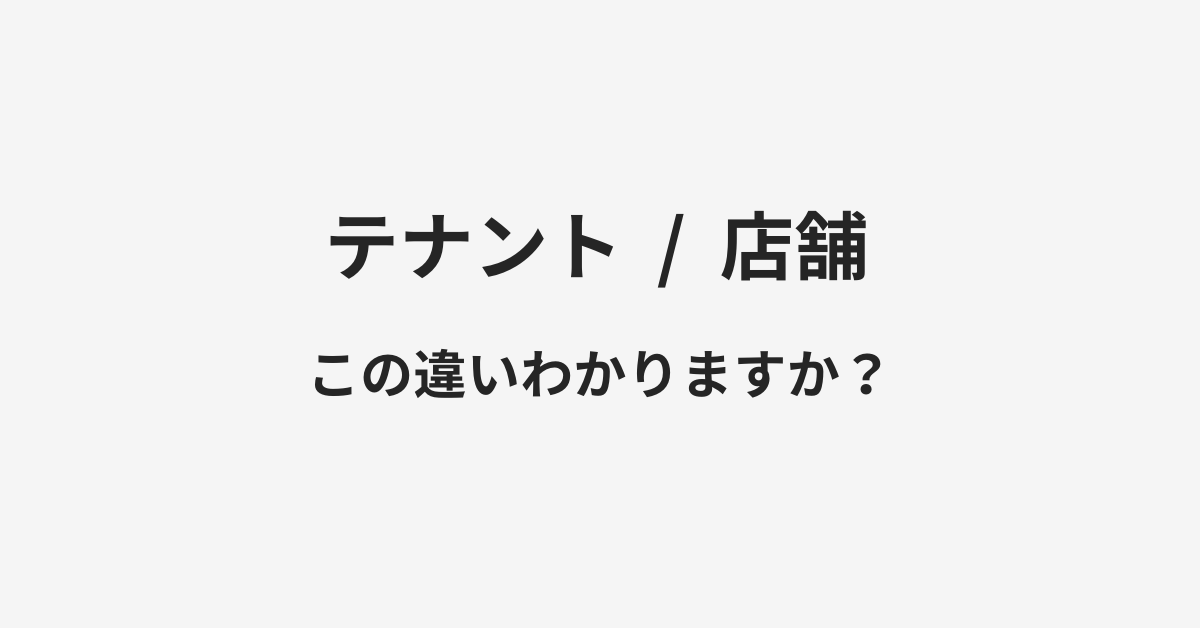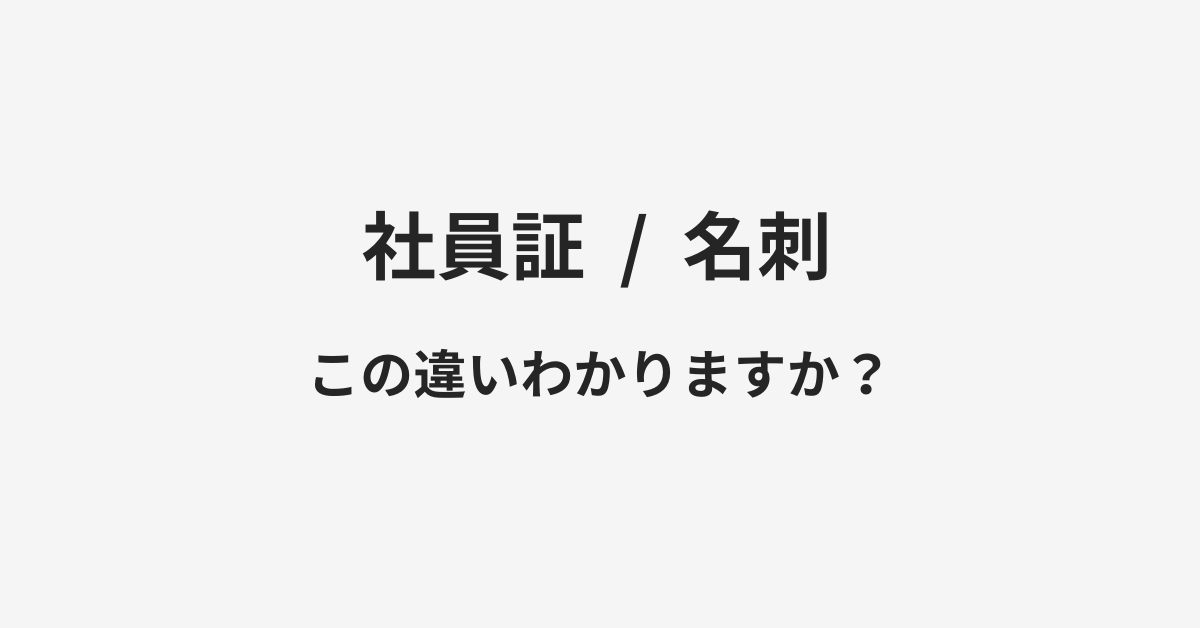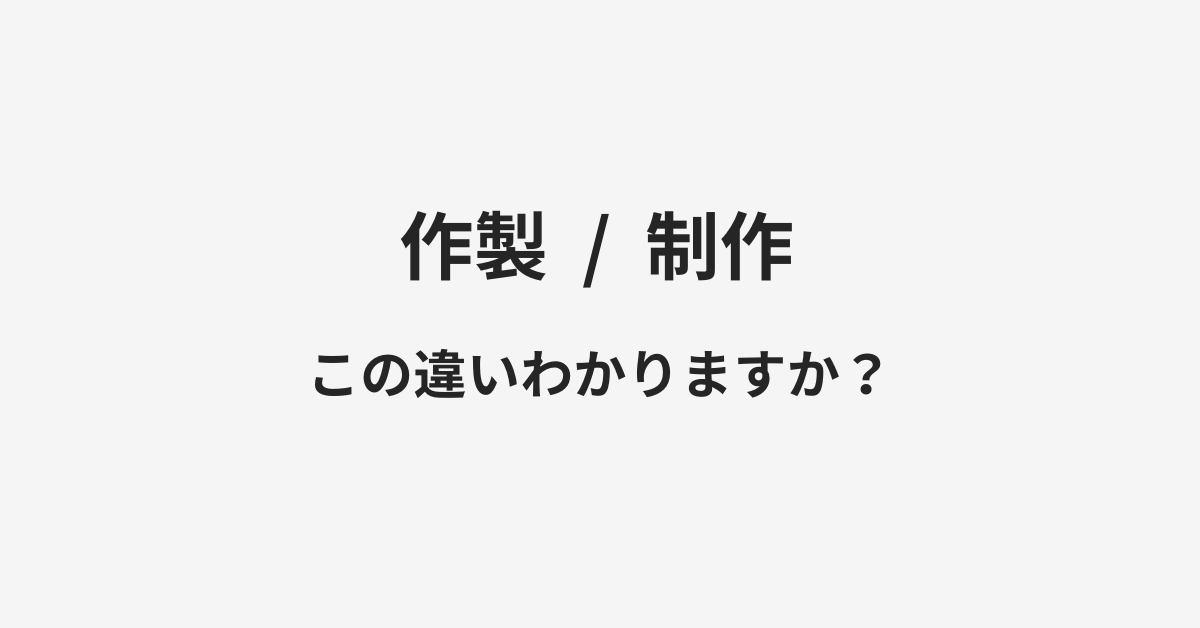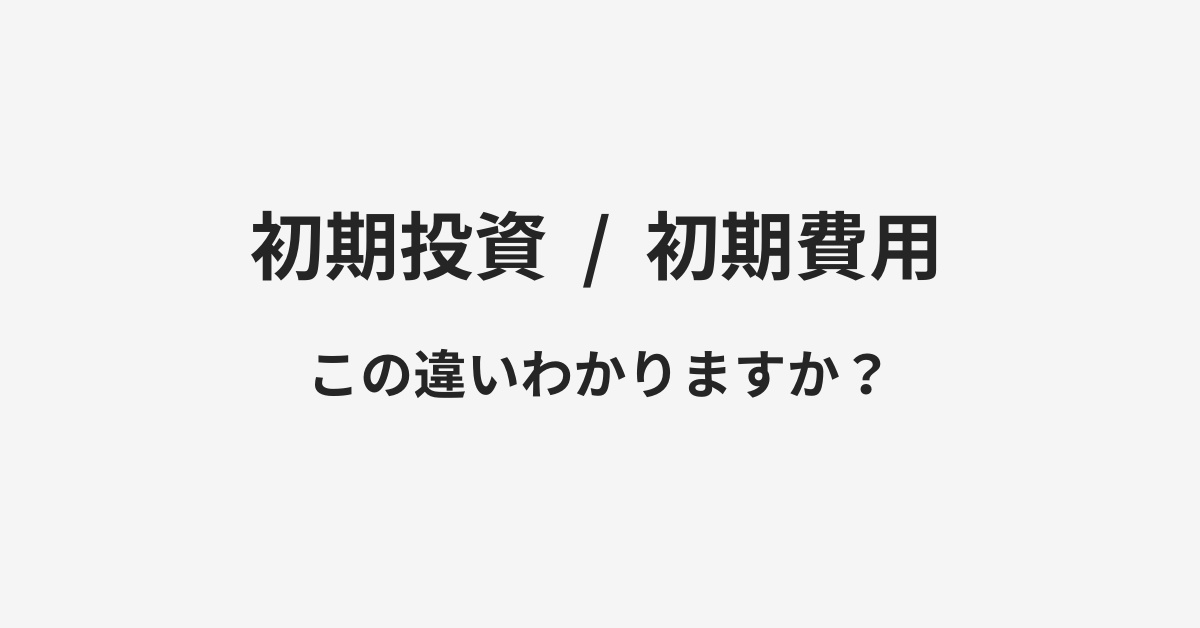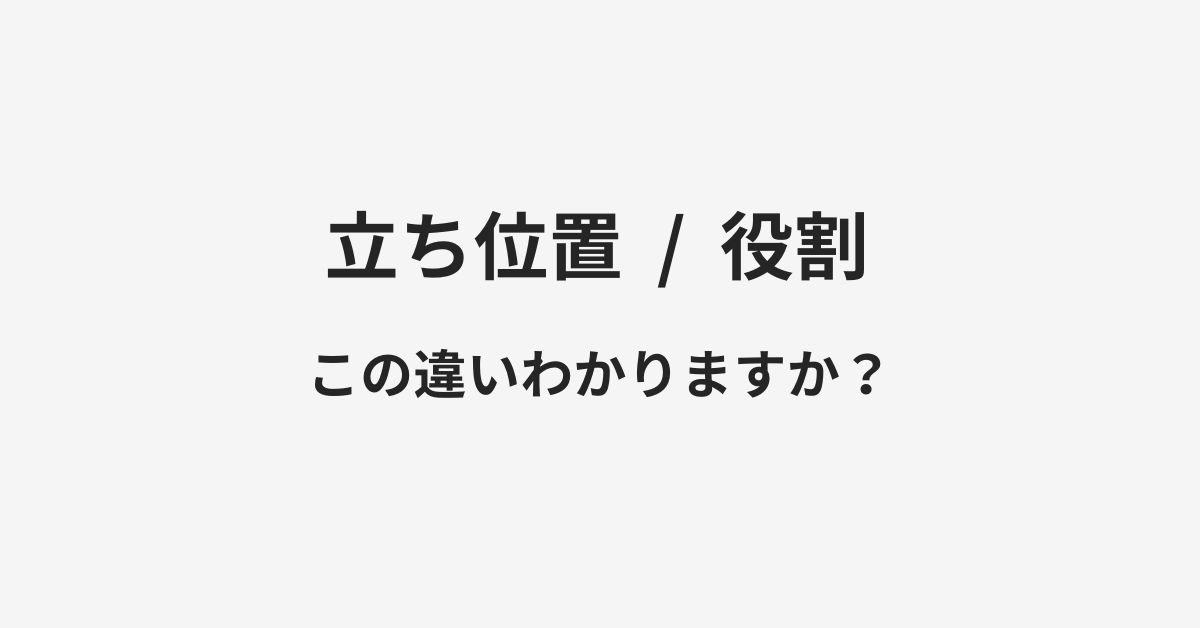
【立ち位置】と【役割】の違いとは?例文付きで使い方や意味をわかりやすく解説
立ち位置と役割は、ともに個人や組織の位置づけを表す言葉ですが、その意味合いには違いがあります。立ち位置は、主に社会や組織の中での相対的な位置や状況を指し、権限や責任の範囲を示唆します。役割は、期待される行動や貢献を表し、果たすべき義務や機能に焦点を当てます。立ち位置が個人や組織の立場や状況を表すのに対し、役割はその立場に基づいて期待される行動を表します。立ち位置は変化しにくい傾向があるのに対し、役割は状況に応じて変化することがあります。