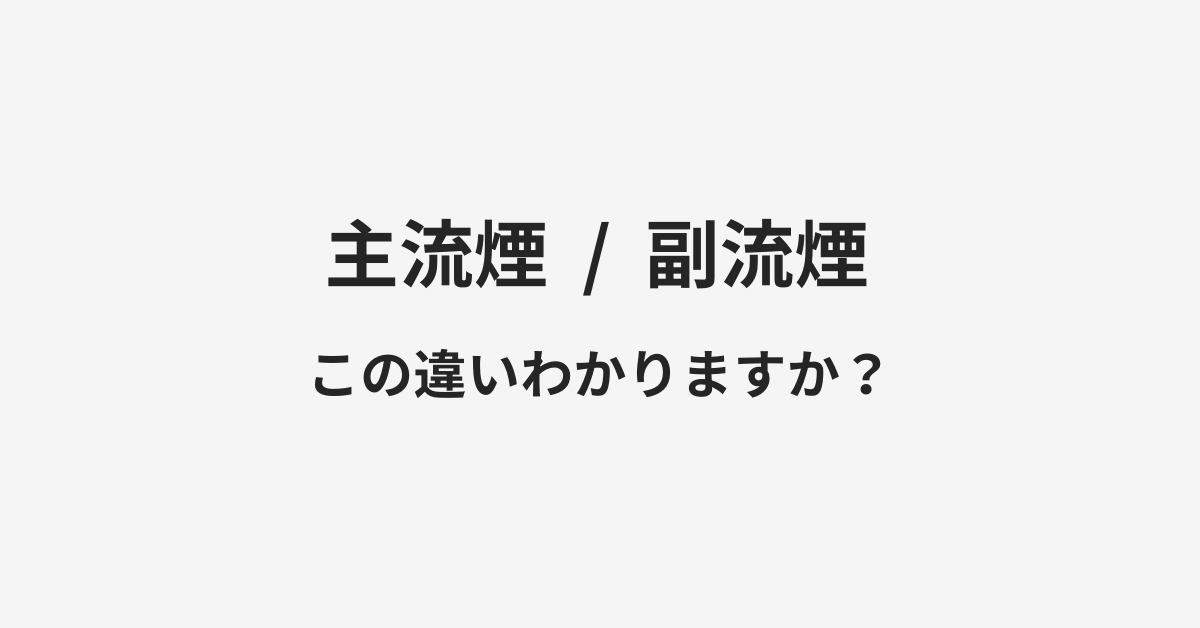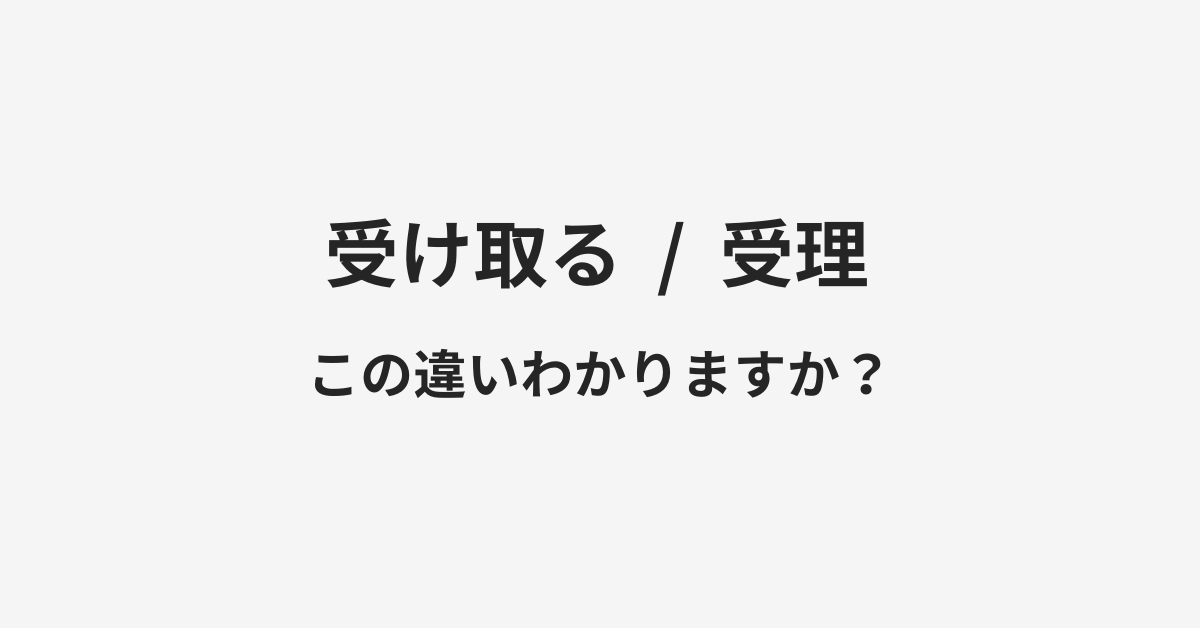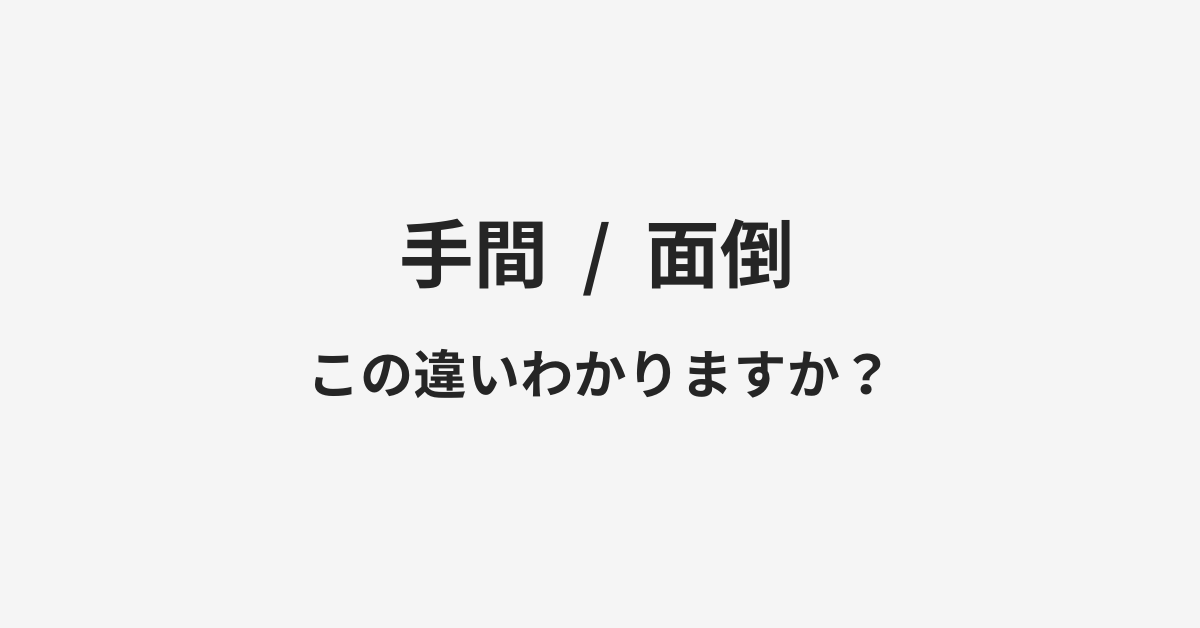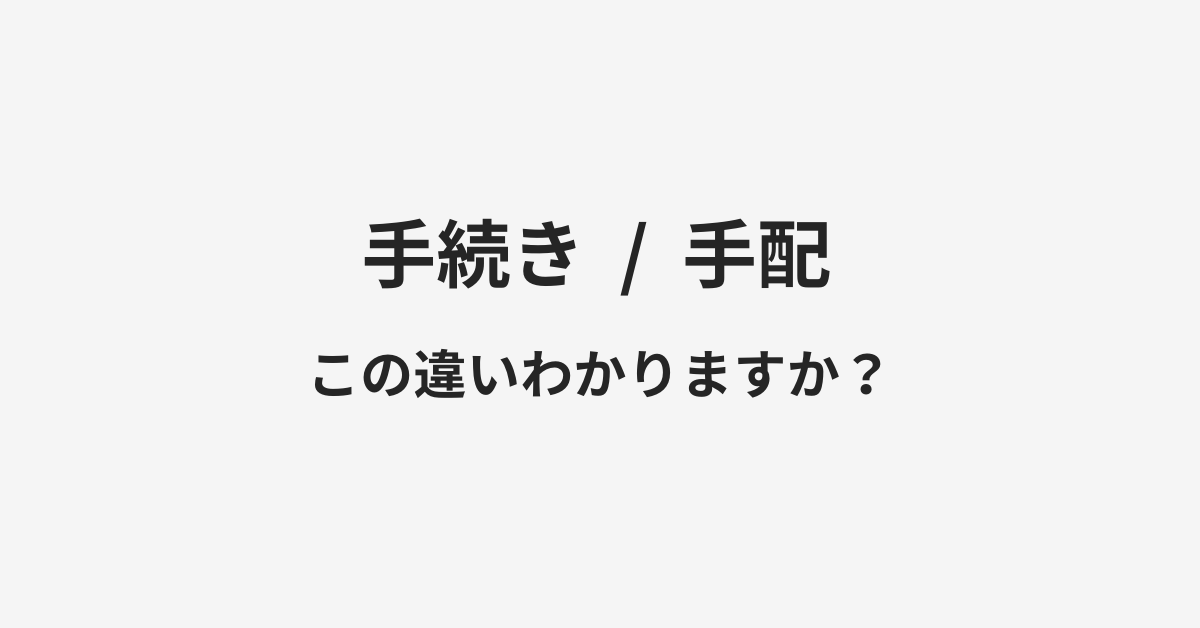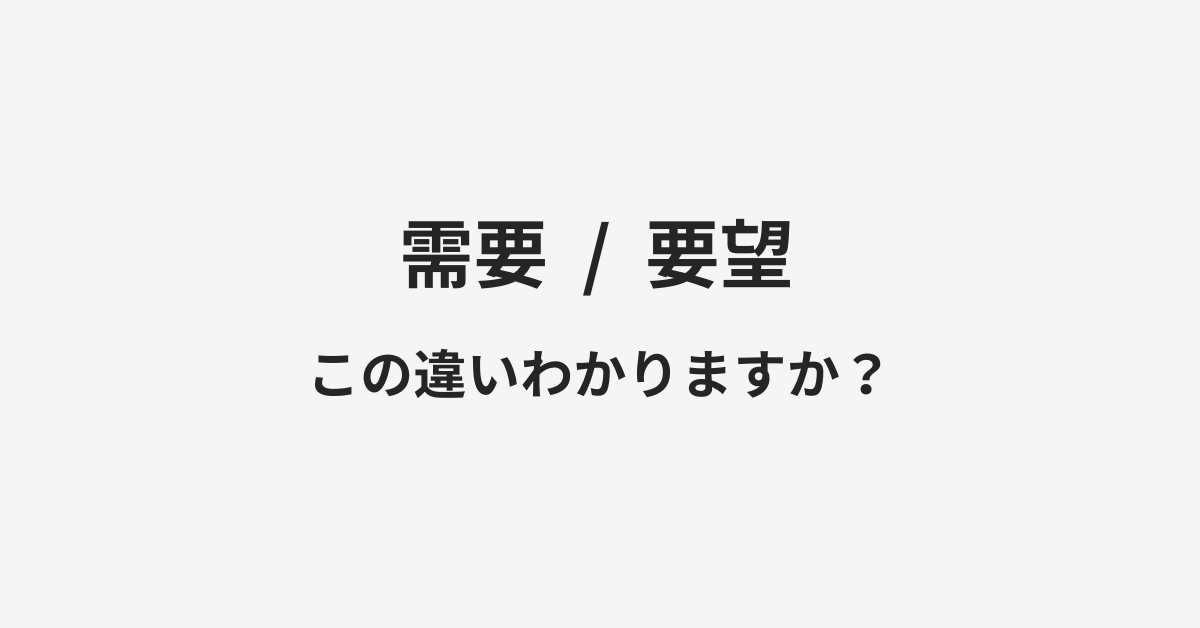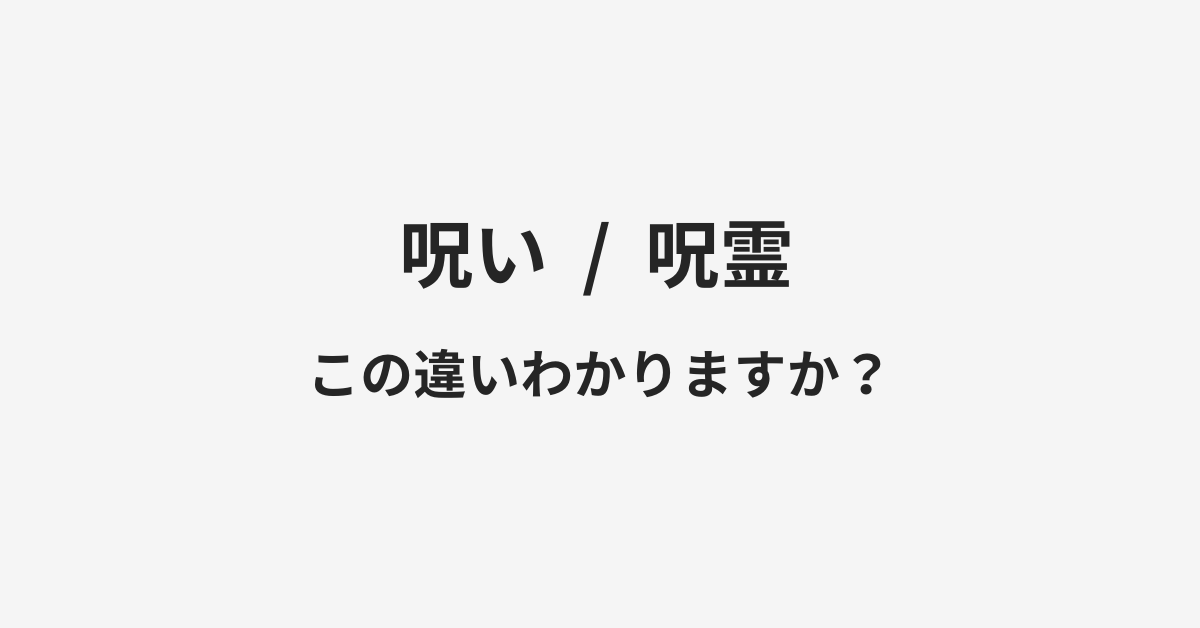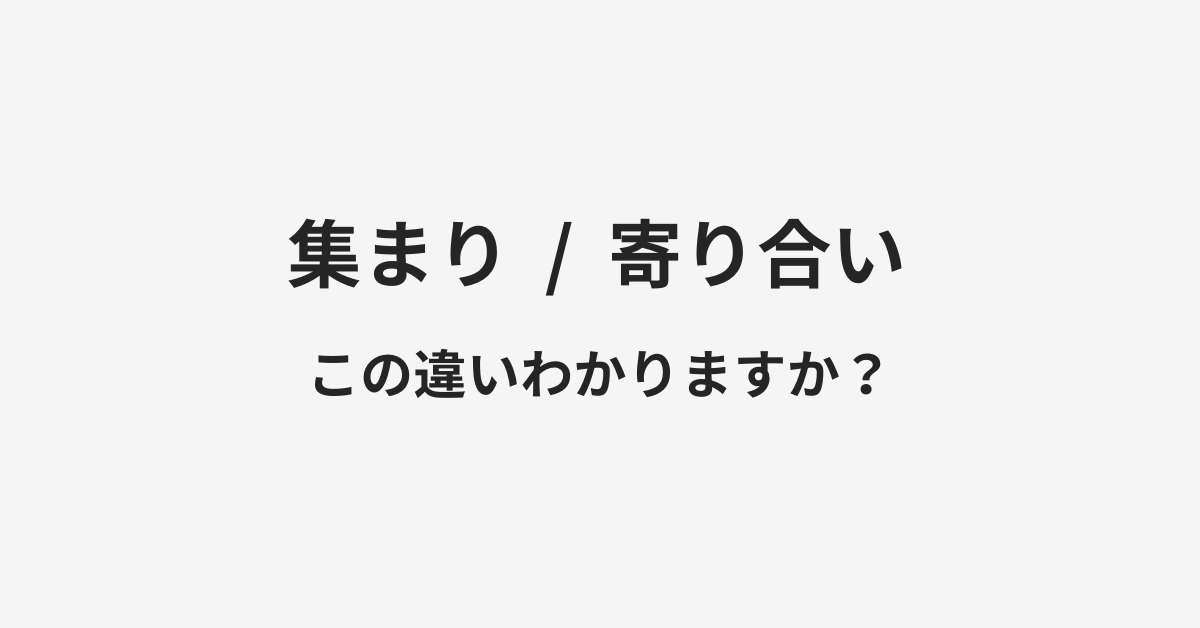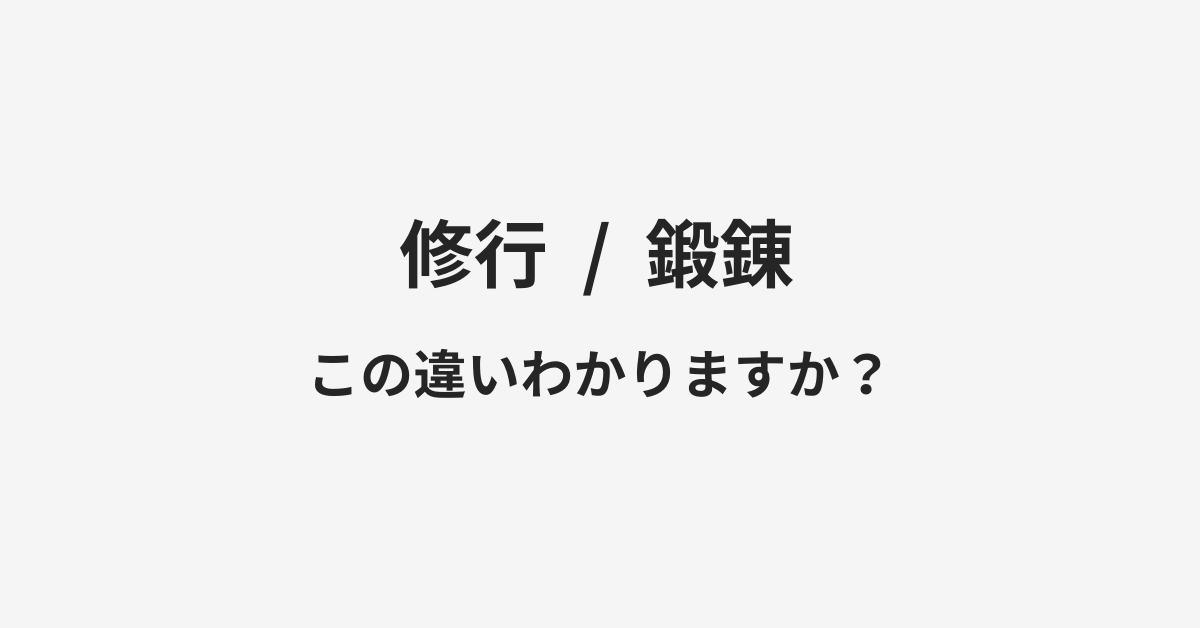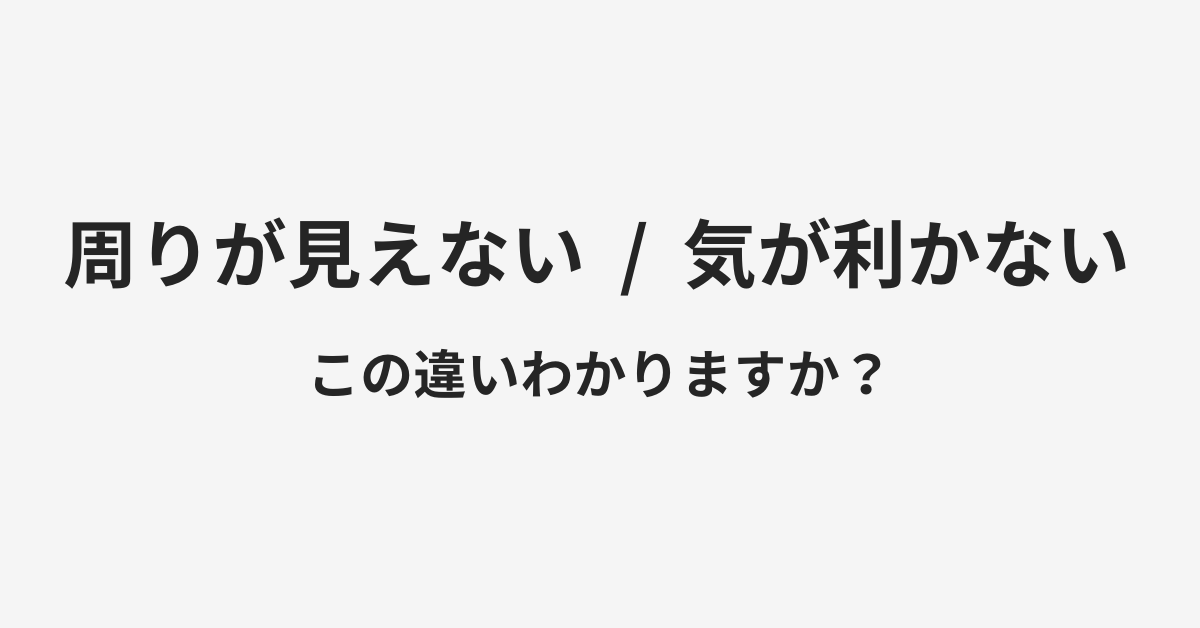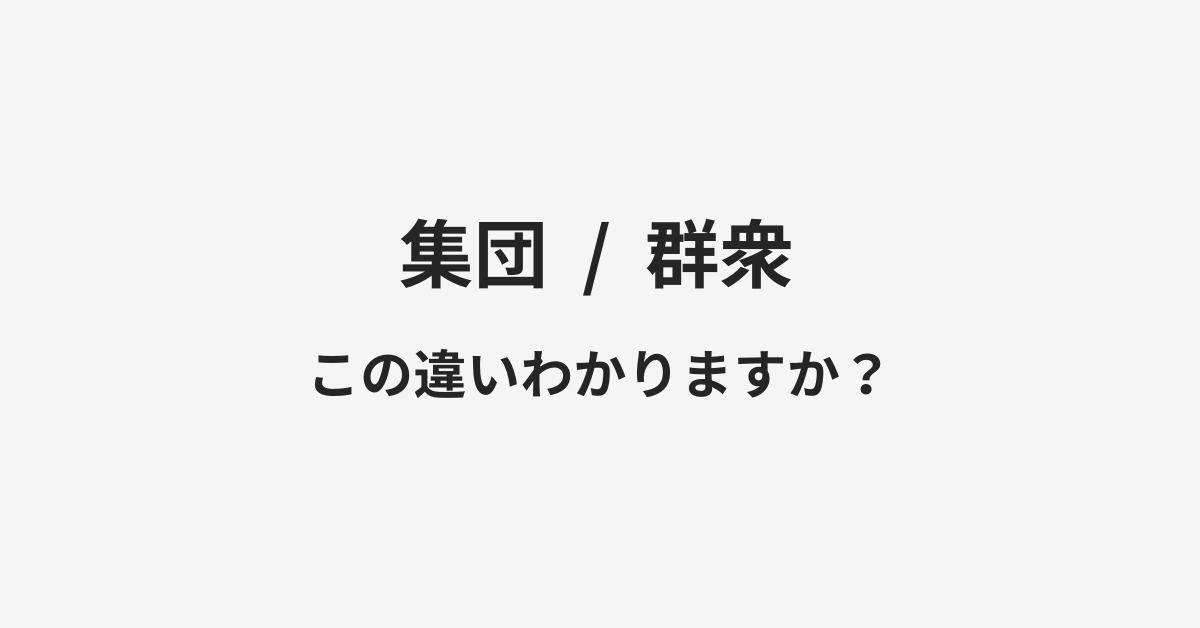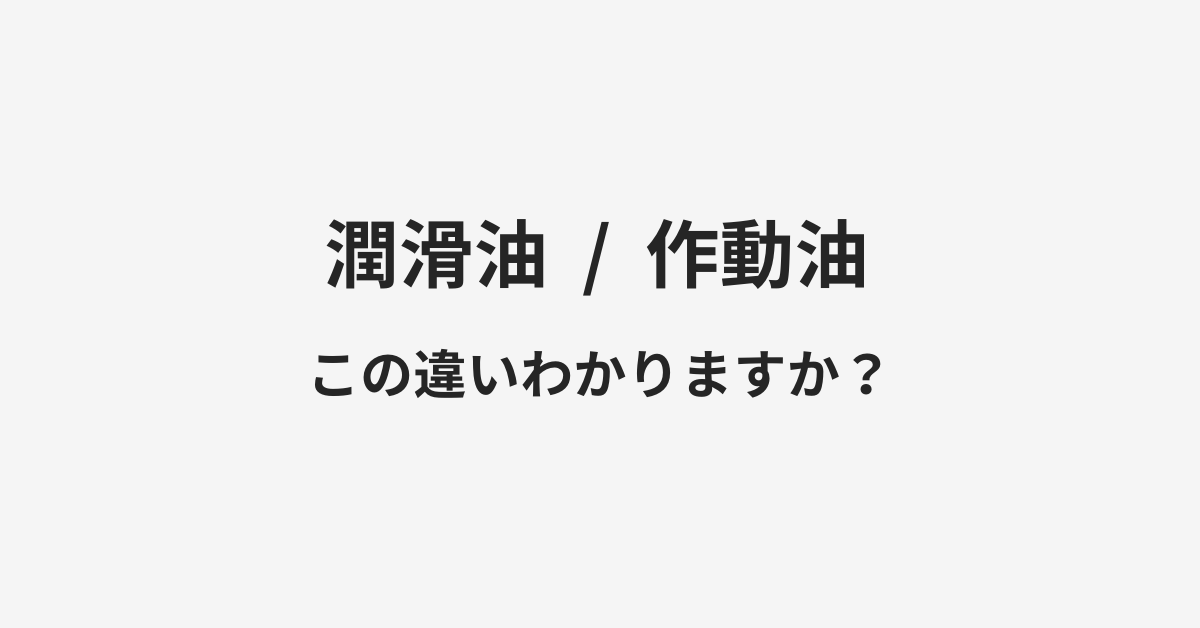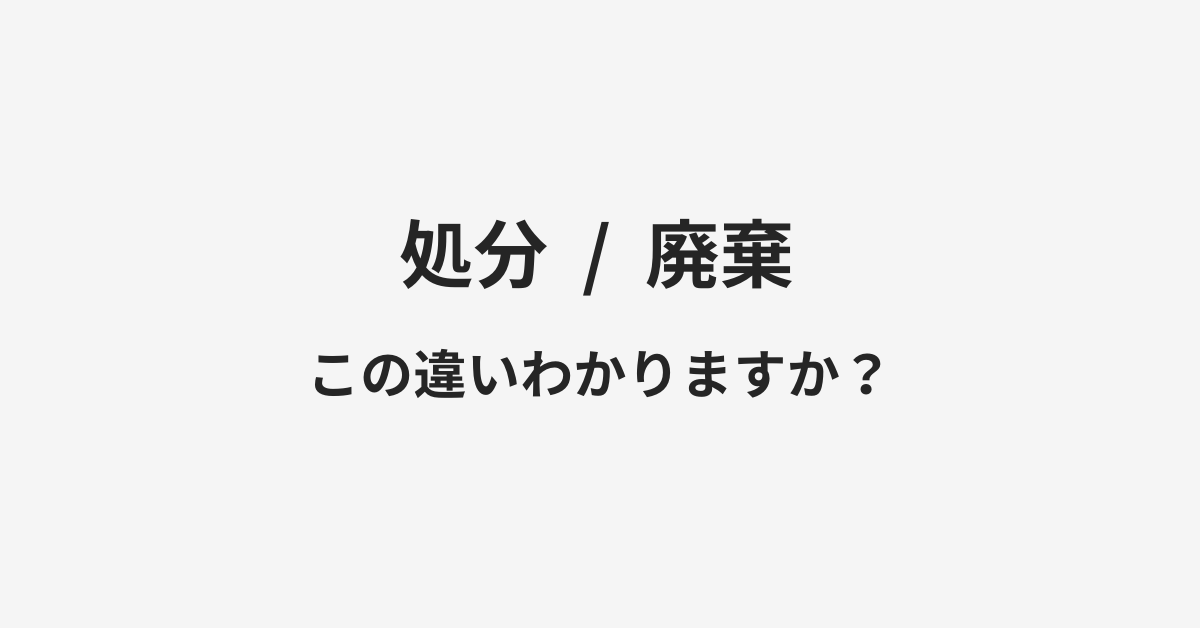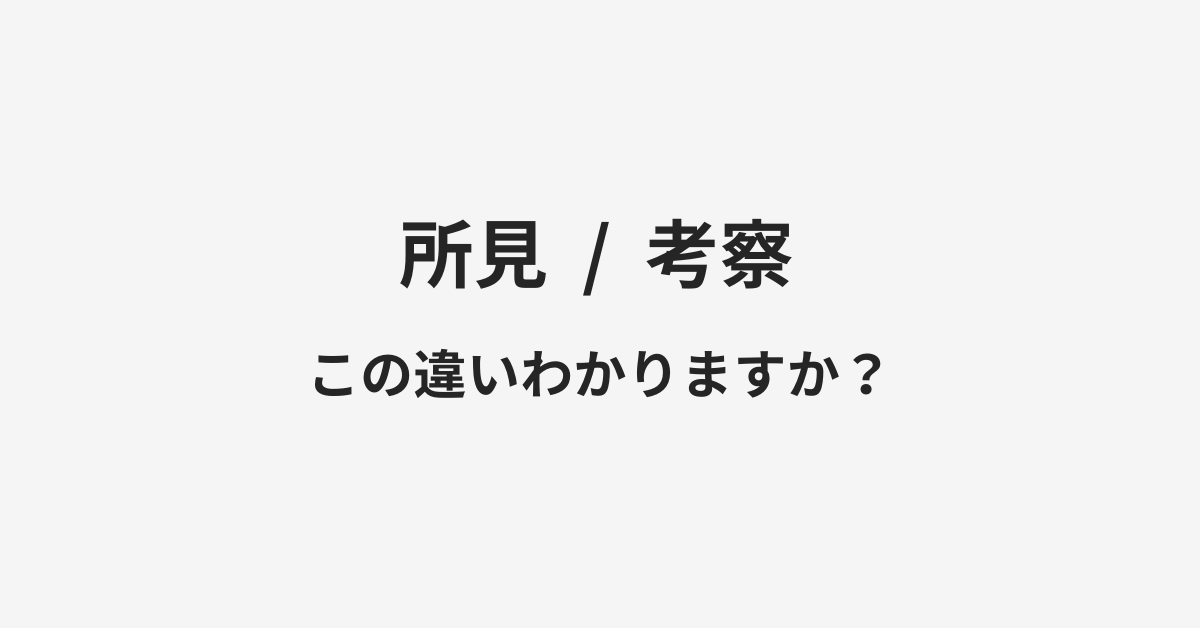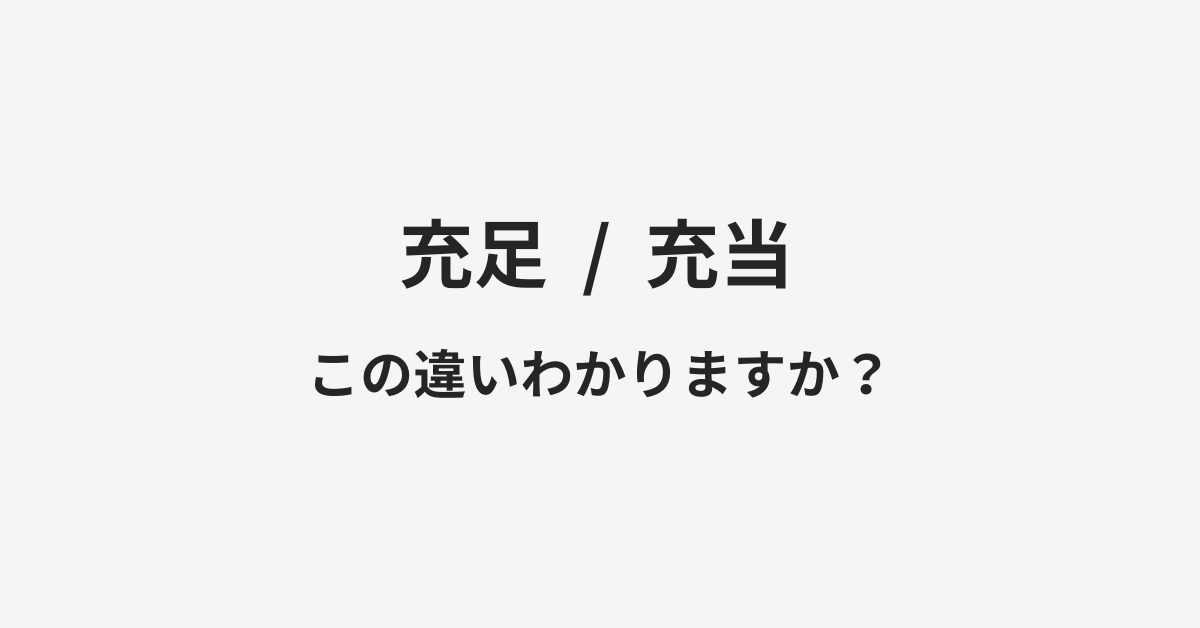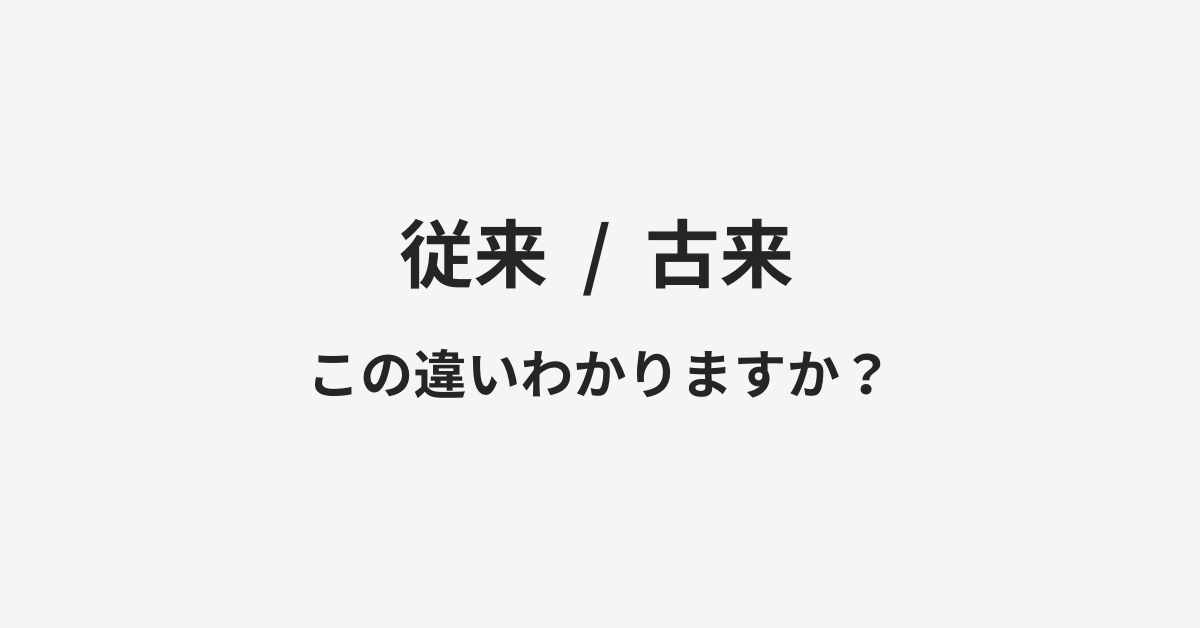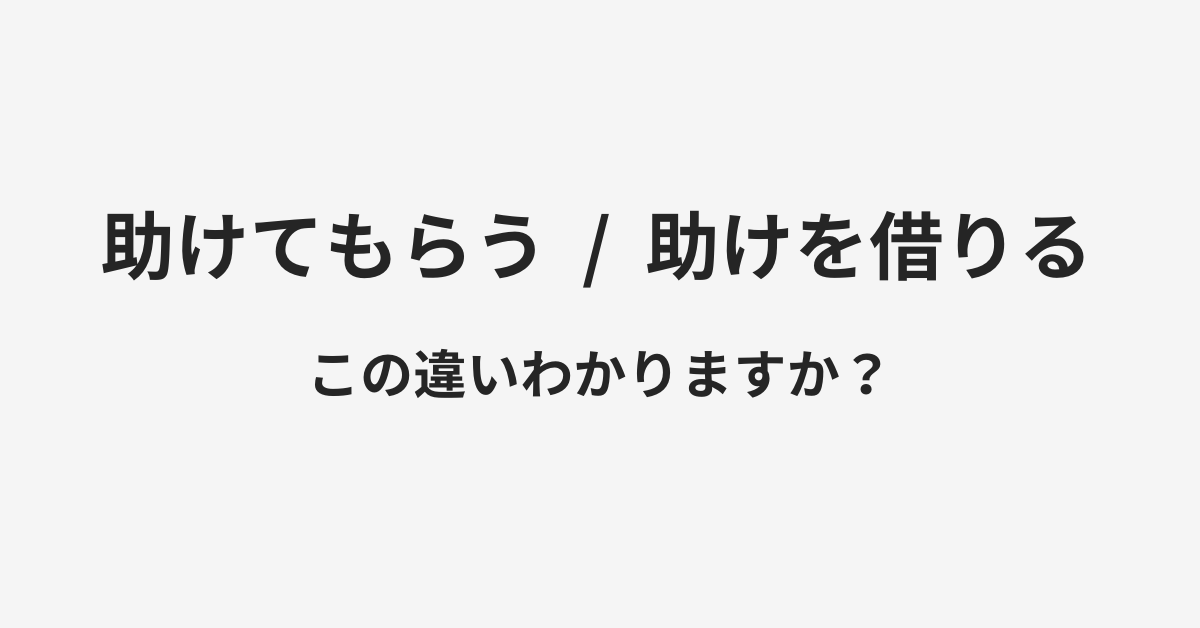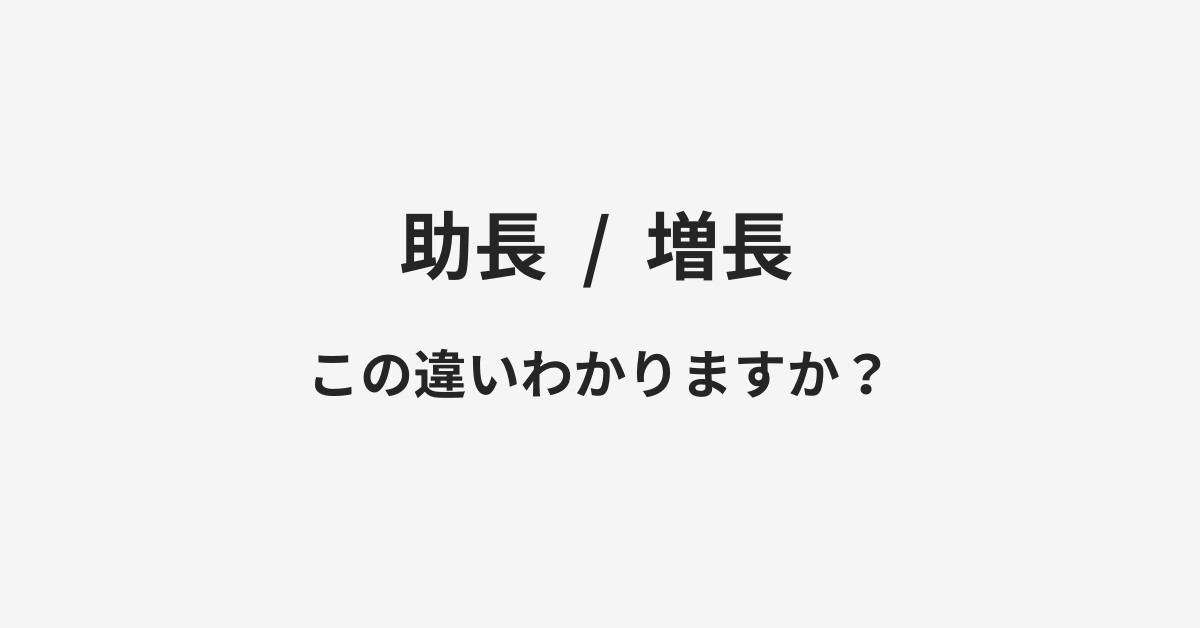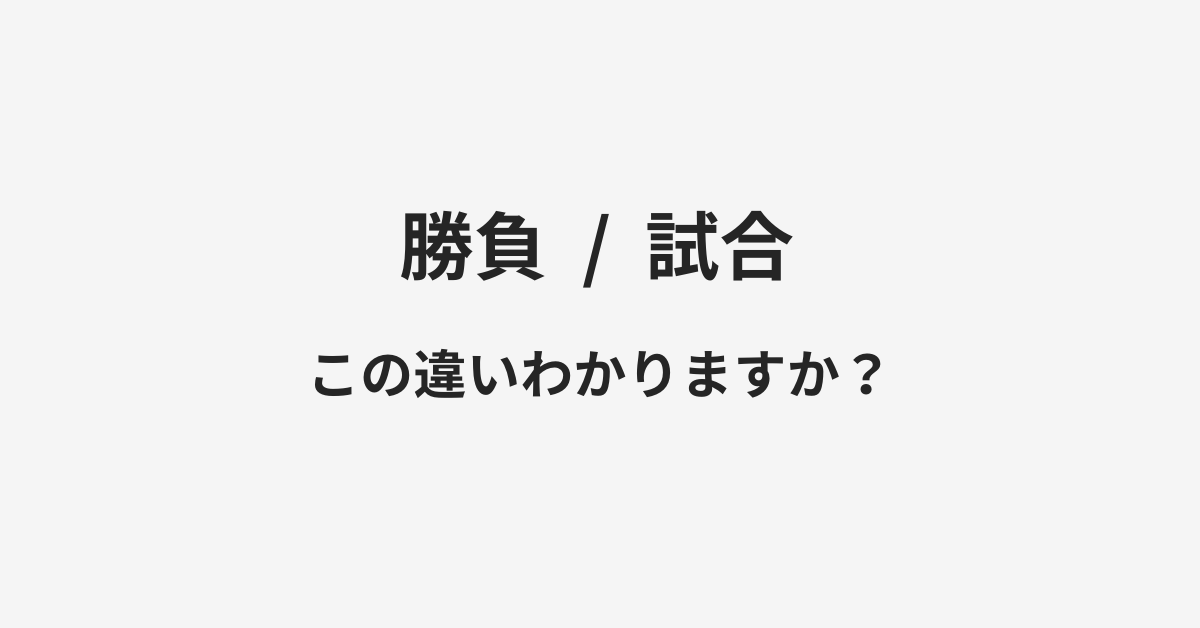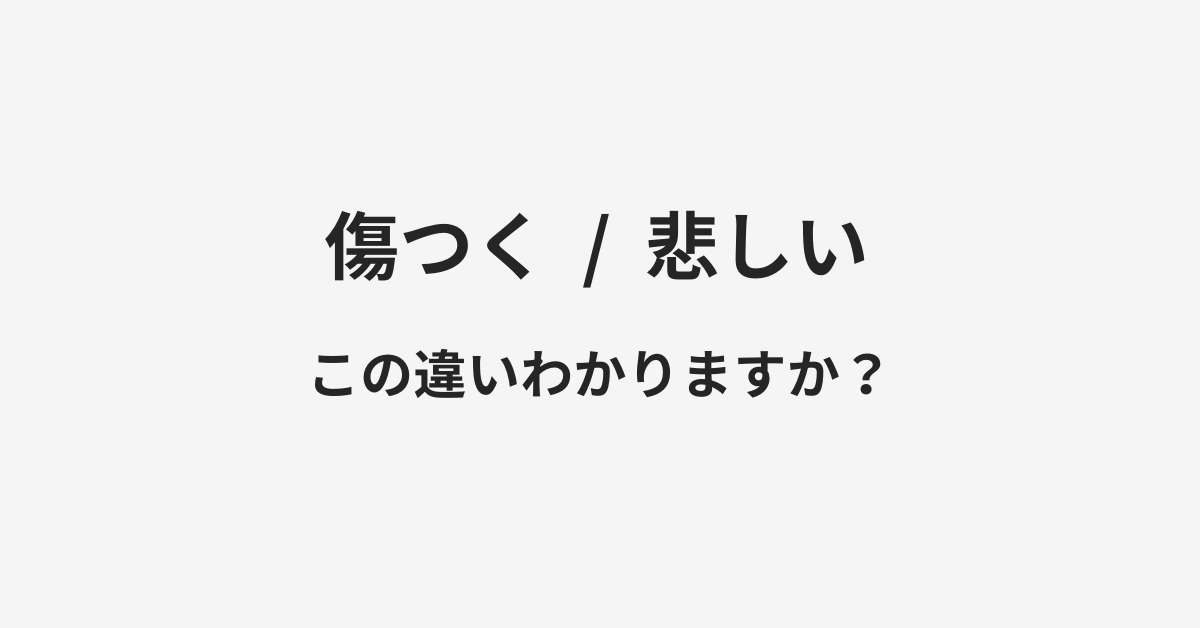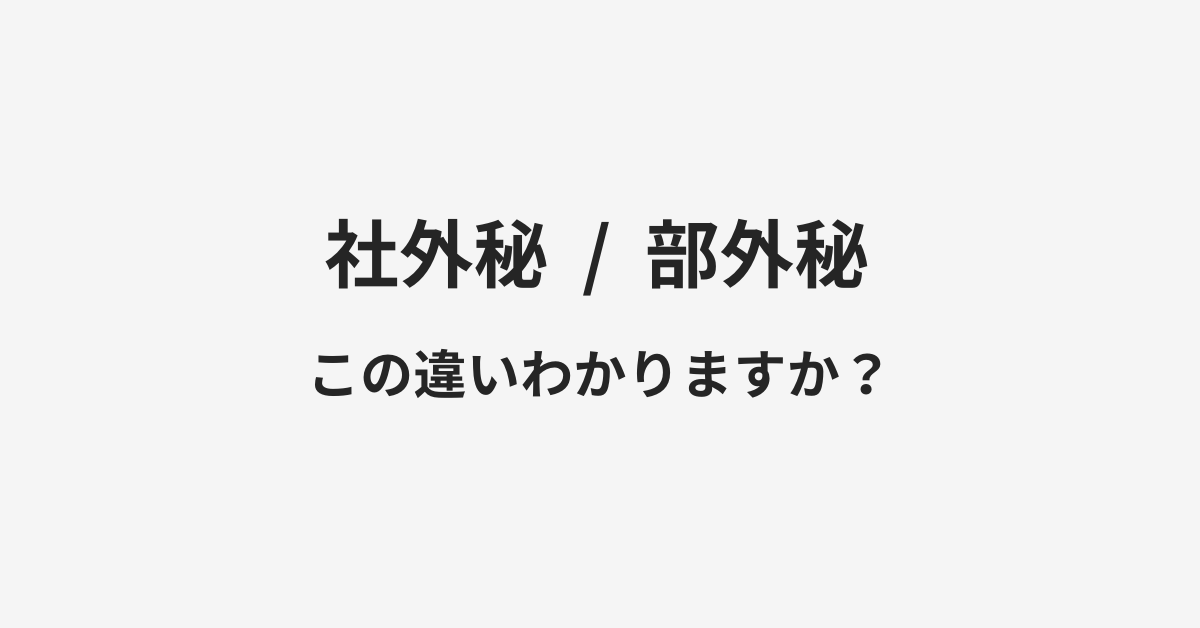
【社外秘】と【部外秘】の違いとは?例文付きで使い方や意味をわかりやすく解説
社外秘と部外秘は、ともに情報の秘匿性を示す言葉ですが、その対象となる範囲に違いがあります。社外秘は、企業や組織の外部に対して秘密を保持することを指し、社内の情報を外部に漏らさないことを目的としています。部外秘は、特定の部署や関係者以外に情報を公開しないことを指し、必ずしも社外への情報流出を防ぐことを目的としていません。社外秘が、企業や組織全体の秘密保持を重視するのに対し、部外秘は、社内の限定的な範囲での秘密保持に重点を置いている点が異なります。また、社外秘は法的な責任を伴うことが多いのに対し、部外秘は社内規定によって定められることが多い点も特徴的です。